
喪主とは、葬儀全体を執り仕切る責任者のことをいいます。
喪主になる機会はそう頻繁にはないため、いざ自分が喪主になった時、何をすればよいかわからないと戸惑うことは多いでしょう。
そこで今回は、家族葬で喪主を務める際にやるべきことについて、葬儀前、葬儀当日、葬儀後に分けたチェックリストをご紹介します。
葬儀社の選定からはじまり、葬儀の日程決めや喪主挨拶、金銭管理など多岐にわたる喪主の役割を時系列でお伝えしていきますので、ぜひ参考にしてください。
目次
喪主の役割とは?施主との違い
喪主とは、遺族の代表として参列者への対応を行い、葬儀社との打ち合わせや式の進行管理なども行う、葬儀全体の責任者となる人のことをいいます。また、葬儀当日に限らず、葬儀前後に必要となる行政手続きや各種申請、法要の準備なども喪主が中心になって行います。
ただし、これらのすべてを一人で抱え込んでしまうことは大きな負担になってしまいます。ご家族やご親族、葬儀社とも連携しながら、任せられる部分は任せて、問題なく式が進められるよう全体を把握していくことが大切です。
ちなみに葬儀費用は、喪主が負担することが一般的ですが、遺族で分担するケースもあります。誰が葬儀費用を支払うかについては、ご家族の状況に応じて臨機応変に対応しましょう。
施主との違いは?
葬儀によっては、喪主と施主がいる場合があります。この場合の施主とは、実務的な責任者であり、葬儀費用を負担する人のことを意味します。
具体的には、若い子どもやご高齢の方が喪主となった場合に、親族や家族の誰かが施主となり、事務手続きや経済的負担を担うというケースが多くなっています。
喪主は誰がやるの?
誰が喪主を務めるかに関して明確な決まりはありませんが、慣例的に故人の配偶者または子どもが務めることが多くなっています。ちなみに、一般的に推奨されている優先順位は以下の通りです。
配偶者→長男→次男以降の直系男子→長女→次女以降の直系女子→両親→兄弟姉妹→友人・知人
ただし、故人が遺言でこの人に喪主をやってほしいと指名していた場合は、その遺志が最優先されます。
とはいえ、配偶者が高齢であったり、長男が遠方に住んでいたりして喪主を担うことができない場合もあると思います。そのため実際は、それぞれの家族の状況に合わせて柔軟に決められることも多いです。
家族葬で喪主がやることチェックリスト
葬儀前、葬儀当日、葬儀後に分けて、喪主のやるべきことをご紹介します。
葬儀前に喪主がやるべきこと
まずは、葬儀前に喪主がやるべきことについてです。
・安置場所の決定
・遺影の準備
・葬儀社との打ち合わせ
・宗教者への連絡・日程調整・読経依頼
・参列者の範囲決定・訃報連絡・案内状送付
・死亡届の記入・提出と火葬許可申請
・会食の手配
・受付係・会計係の選任
【葬儀社の選定】
最初に行うことは、葬儀社の選定です。依頼する葬儀社を決めて連絡をすると、葬儀社が病院や施設等に迎えに来てくれるので、希望する安置場所にご遺体を搬送してもらいます。
【安置場所の決定】
どこにご遺体を安置するかについては、あらかじめ決めておいた方がよいでしょう。安置場所の選択肢としては、葬儀社の安置施設やご自宅などがあります。自宅安置の場合は条件もあるため葬儀社と相談しながら進めていくとよいでしょう。
【遺影の準備】
葬儀で使用する遺影写真のデータは、なるべく早めに葬儀社に渡す必要があります。葬儀社との打ち合わせの際に渡せれば一番スムーズなので、事前にふさわしい写真データを探しておくと安心です。すぐに見つからないという場合は、葬儀社にいつまでに渡せば間に合うかを確認し、期限内にデータを渡せるよう手配しましょう。
【葬儀社との打ち合わせ】
ご遺体を安置した後、葬儀社との打ち合わせを行います。打ち合わせでは葬儀の規模や「家族葬」などの形式、祭壇や棺などの葬送用品のグレードなどを決め、必要な費用を割り出すと同時に、葬儀日程や会場も決めることになります。
|葬儀社との打ち合わせで喪主がやるべきこと|
・日時・会場の決定
・宗派の確認
・葬儀の規模やプランの決定
・祭壇や棺などの種類を決定
・会葬御礼や返礼品の手配
・会食の有無の確認・手配
・遺影の確認
・費用の確認 など
【宗教者への連絡・日程調整・読経依頼】
葬儀日程は、火葬場の空き状況やご家族のご都合、そして宗教者のご都合を考慮して決められます。この時、宗教者への日程調整を行うのも喪主の役割です。菩提寺がある場合は菩提寺の僧侶に連絡をし、逝去の事実を伝え、葬儀での読経を依頼するとともに、ご都合のよい日程をお伺いしましょう。
【参列者の範囲決定・訃報連絡・案内状送付】
葬儀に参列していただく人を決めて、訃報の連絡をします。家族葬の場合、参列いただかない方への訃報連絡は葬儀後の事後報告とすることが一般的ですので、参列いただく方にのみ電話等でご連絡をしましょう。
【死亡届の記入・提出と火葬許可申請】
死亡届の提出と火葬許可申請は、葬儀社が代行してくれることも多いので、任せられるのであれば任せてしまったほうが安心です。
ただし、死亡届の記入は喪主が行います。医師から受け取った死亡診断書の左側が死亡届になっているので、そこに必要事項を記入しましょう。この書類は、相続や事後手続きなどでも必要になることがあるため、記入が終わったら10枚程度コピーを取っておくと安心です。
もし、ご自身で申請を行う場合は、この書類を故人の住民票のある市区町村役場に提出することになります。
【会食の手配】
お通夜後に「通夜振る舞い」葬儀後に「精進落とし」といった会食の席を設ける場合、仕出し弁当や懐石料理などの手配が必要です。葬儀社との打ち合わせの際に、相談しておきましょう。
【受付係や会計係の選任】
極小規模な家族葬や、香典を辞退されている家族葬などでは受付を設けないことも多いですが、20名を超える家族葬で香典を受け取る場合は、当日会場で香典の受け取りや返礼品のお渡しなどを行う係を設けることも検討しましょう。
受付係や会計係は、参列者の中から選任します。遺族席に座らないような遠い親族または友人・知人などの関係者に、喪主から事前に依頼しておきましょう。
葬儀当日に喪主がやるべきこと
次は、葬儀当日に喪主がやるべきことについてです。
・僧侶の対応
・参列者対応
・喪主挨拶
・香典の受け取り管理
・会葬御礼・返礼品(当日返しの場合)の準備
・会食でのおもてなし
【会場の確認】
喪主は開式の1〜2時間前には会場入りし、会場の導線や席次、供花や返礼品などの準備状況、式の流れなどを葬儀社と打ち合わせをしながら確認します。
【僧侶の対応】
僧侶が到着したらお迎えにあがり、控え室へご案内します。お布施もこのタイミングでお渡しできるとよいでしょう。お布施をお渡しする時には「本日はどうぞよろしくお願いいたします」など一言添えると丁寧です。また直接手渡しはせず、切手盆または袱紗に乗せてお渡しします。
【香典の受け取り管理】
受付で受け取った香典は、最終的に喪主や遺族の手元に引き渡されます。集計をしておくのか、どのタイミングで引き渡すのかなど、香典の管理方法をどうするかは、事前に決めて係に伝えておくと安心です。
【会葬御礼・返礼品(当日返しの場合)の準備】
参列者にお渡しする会葬御礼や返礼品が受付に準備されているかを確認しましょう。もし、香典を受け取る場合で、「当日返し」をされる場合は、会葬御礼と返礼品を一緒にお渡しすることになります。
【参列者対応】
参列者がお見えになったら、適宜挨拶をして迎え入れます。
【喪主挨拶】
開式と閉式時に、遺族を代表して挨拶を行います。喪主挨拶では、事前に内容を考えたメモなどを用意しておくと安心です。挨拶は長々とはせず、長くても3分程度に収めるようにしましょう.。
【会食でのおもてなし】
会食会場へのご案内や座席の指示、最初と最後に喪主挨拶を行うなど、会食会場でのおもてなしも喪主の役割の一つです。ちなみに、会食の席での献杯の音頭は喪主がとる場合もあれば、事前に故人と親しかった人にお願いしておく場合もあります。ご自身で献杯を行わない場合は早めに依頼しておきましょう。
葬儀後に喪主がやるべきこと(四十九日法要まで)
葬儀が終わってからも、喪主のやるべきことは続きます。
・各種申請手続き
・四十九日法要と納骨の準備
・法要当日の持ち物の準備
【香典帳の整理と香典返しの手配】
香典を辞退しなかった場合は、誰からいくらいただいたかを記録してある香典帳を整理し、香典返しの手配をします。もし、葬儀当日に当日返しを行っていた場合は、高額な香典をいただいた方に対してのみ追加の返礼品を用意すれば問題ありません。
【各種申請手続き】
年金受給停止手続きや、健康保険の資格喪失届、世帯主変更届などの手続きを行います。それぞれ死亡日から数日〜2週間以内に行わなければならないなど期限付きのものも多いため、期限内に行うようにしましょう。
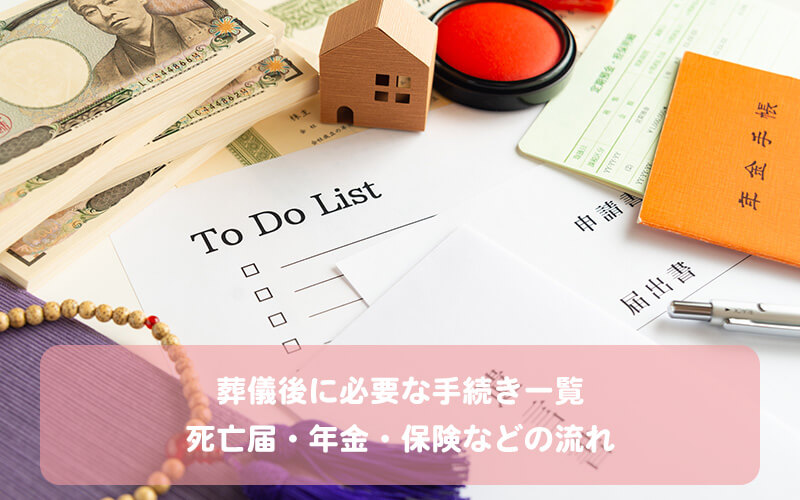 |
葬儀後に必要な手続き一覧|死亡届・年金・保険などの流れ 大切な方を亡くされた後にご家族様がするべきことは多岐にわたります。お身内を亡くされ、ただでさえご不安な中、事務手続きをこなすことは大変なことですが、期限のある手続きも多いため、優先順位をつけて一つひとつ片付けていくことが大切です。 |
【四十九日法要と納骨の準備】
四十九日法要と納骨式は同日に行うことが一般的です。まず、納骨先(お墓や納骨堂など)を決めたら、宗教者や納骨先と法要や納骨式の日程調整を行います。
日程が決まったら、法要に参列いただく方へ日時や会場等詳細をご案内しましょう。また、参列者へお渡しする引き出物の準備や、当日会食の席を設ける場合はその手配なども必要です。
【法要当日の持ち物の準備】
位牌、遺影、ご遺骨、供花や供物など、法要当日に持参するものを揃えておきましょう。宗教者にお渡しするお布施も忘れずに準備しておきます。
また火葬後に火葬場のスタッフから受け取った埋葬許可証(火葬許可書に押印がされたもの)がないと、納骨ができなくなってしまうので、法要まで大切に保管し、当日は必ず持参するようにしましょう。
家族葬で喪主を務める場合に気を付けること
最後に、家族葬ならではの注意点をお伝えします。
香典や供花等の辞退は明確に伝える
家族葬では、香典返しの手間などを省いて故人とのお別れに集中したいという理由から、香典や供花・供物等を辞退するケースも少なくありません。
それらを辞退する場合は、事前に明確にその旨を伝えておくことが大切です。
具体的には「誠に勝手ながら、香典・供花・供物は固くご辞退申し上げますので、何卒ご理解のほどお願い申し上げます。」など、何を辞退するのかを明記しておくとわかりやすいです。
葬儀に参列いただかない方には事後報告とする
家族葬は、参列者を限定する葬儀のため、葬儀に参列いただかない方への訃報連絡は事後報告とすることが推奨されています。そうすることで、呼ばれていない人が間違えて会場にきてしまうなどのトラブルも防ぐことができます。
喪主挨拶ではアットホームさも意識
一般的な葬儀と違って、身内中心の家族葬では、喪主挨拶も参列者への感謝の気持ちを込めた形式的すぎない挨拶がふさわしいとされています。
親族間の意見を調整する
家族葬は、参列者の数を限定して行う小規模な葬儀です。比較的新しい葬儀でもあるため、伝統や形式を重んじるご親族の中には、違和感を覚える方もいるかもしれません。故人の遺志を尊重することはもちろんですが、家族や親族の希望なども踏まえて、全体を調整しながら葬儀プランを決めていくことが大切です。
参列できなかった人への配慮も忘れない
家族葬では、葬儀に参列したくてもできない人がどうしても出てきてしまいます。
特に、近所の方や故人との関係性の深かった方などへは、後日挨拶に伺ったり、葬儀後の事後報告で、「故人の遺志により家族葬にて葬儀を執り行いました」など、納得いただけるような理由を添えたりするといった配慮も忘れないようにしましょう。
喪主は遺族の代表。事前に役割を知って心の準備をしておこう
どんなに小規模な家族葬であっても、喪主は遺族の代表です。事前に喪主がやるべきことを知っておくことで、葬儀やその後の法要までをスムーズに進めることができます。家族葬も一般葬も喪主の基本的な役割は変わりませんが、家族葬ならではの注意点もあるため、それに気を付けて進めていくことが大切です。
喪主の役割や、やるべきことについてご不安があれば、葬儀社の事前相談を活用することもおすすめです。
家族葬のタクセルでは、葬儀に関わる事前相談を無料で行なっております。専門の相談員が、24時間365日ご相談を承っておりますので、お気軽にご相談ください。
家族葬のタクセルの無料相談はこちらから
栃木・茨城・静岡・愛知・群馬・宮城のご葬儀は、家族葬のタクセルで
家族葬のタクセルでは、栃木・静岡・愛知・群馬・宮城での家族葬や一日葬を安心の低価格で承っています。まずはお見積もりだけでも、お気軽にお問い合わせください。
お見積もり・葬儀のご依頼は下記までお電話ください。
栃木県・茨城県 0120-633-009
静岡県 0120-83-3020
群馬県 0120-880-514
愛知県 0120-574-247
宮城県 0120-486-141
家族葬のタクセル ホームページはこちらから
家族葬のタクセルのお葬式
✔️少人数対応の家族葬専用の式場
✔️お近くの火葬場で直葬・一日葬も対応
✔️費用を抑えた低価格のお葬式を実現
✔️葬儀前から法要まで充実のサポート
✔️24時間365日、いつでもご依頼・ご相談可能
✔️中部エリアでテレビCM放映中
24時間365日、いつでもお待ちしています。

 お急ぎの方へ
お急ぎの方へ 無料相談
無料相談 資料請求・
資料請求・ 供花注文
供花注文