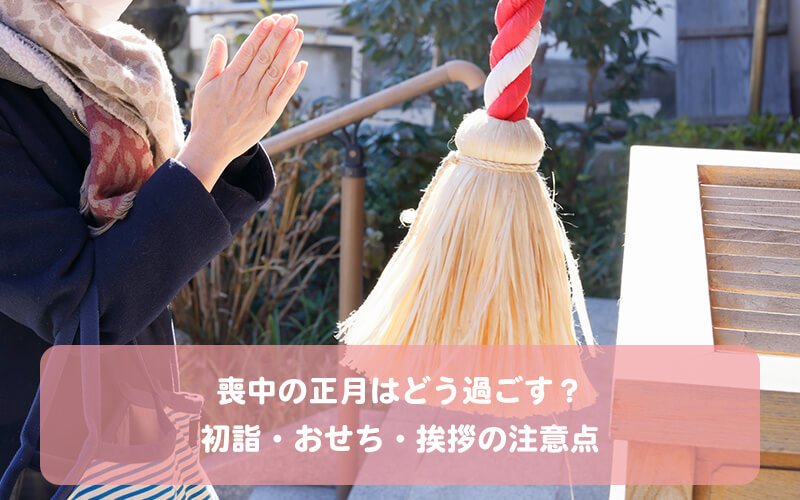
大切な方を亡くされて、喪中の中で迎えるお正月には、実は避けた方がよいことがあります。
「初詣には行ってもいいの?」
「おせちは食べても大丈夫?」
など、疑問に思っていることも多いのではないでしょうか。
そこで今回は、喪中のお正月の過ごし方について解説します。
喪中期間中の年越しそばやおせち、お雑煮、初詣、お年玉、年賀状などといった年末年始ならではの慣習を控えるべきかという疑問について、推奨されている対応をお伝えしますので、ぜひ参考にしてください。
喪中期間とは?いつまで?
「喪中(もちゅう)」とは、近親者が亡くなった際に、故人を偲び身を慎む期間のことをいい、一般的には、故人が亡くなってから一周忌法要が済むまでの約1年間が喪中期間とされています。
江戸時代〜明治時代は、喪中期間や喪中の過ごし方が身分ごとの規則として存在していましたが、現代においては、古くからの慣習として根付いている程度にとどまり、遺されたご遺族が、故人のことを想い、失った悲しみと向き合うための期間としてとらえられています。
「忌中」との違い
同じく亡くなった方を偲び、身を慎む期間に「忌中(きちゅう)」がありますが、忌中は、故人がお亡くなりになってから四十九日法要(神式では五十日祭)を迎えるまでの期間を指し、この期間中は結婚式などのお祝い事への出席や主催、神社への参拝、派手な行動、お中元やお歳暮などを送ることなどは控えたほうがよいとされています。
喪中かどうかわからない場合の確認方法
なかには、ご自身が喪中に該当するかわからないという方もいると思います。喪中とは、故人との続柄が2親等以内かどうかが目安となります。つまり、故人の配偶者、父母、兄弟姉妹、子ども、孫、祖父母、兄弟の配偶者などがそれにあたります。
喪中期間中の過ごし方
喪中期間中は、忌中ほど厳格ではありませんが、結婚式への出席などのお祝いごとや豪華な旅行、派手なイベントなどはなるべく避けることが推奨されています。お中元やお歳暮は、お祝い事ではないため喪中には送ってもよいとされていますが、水引のない白無地の奉書紙を用いるなどの配慮が必要になります。
喪中期間中のお正月の過ごし方
新しい年を迎えるお正月は、一年のはじまりを祝う日本の伝統行事です。おせちを食べたり初詣をしたり、お祝い事の慣習がたくさんありますが、お祝い事を控えるべきとされている喪中期間中には注意が必要です。
ここでは、喪中期間中に年末〜年始を迎えた場合の過ごし方についてお伝えしたいと思います。
年賀状
年賀状は出さずに、11月〜12月初旬までの間に喪中はがき(年賀欠礼状)を出すようにしましょう。喪中はがきには、故人の続柄と亡くなった日付を記載し、「服喪中のため新年のご挨拶をご遠慮させていただきます」という内容にします。
本年〇月〇日 父(○○ ○○)が〇歳にて永眠いたしました
ここに本年中に賜りましたご厚情を深謝申し上げますとともに
明年も変わらぬご厚誼を賜りますようお願い申し上げます
令和〇年十一月
また、もし喪中期間中に年賀状が届いた場合は、松の内(1月7日)を過ぎてから、「寒中お見舞い」としてお返事を書くことが一般的です。その際は、年賀状をいただいたことへのお礼と共に「昨年〇月に○○(続柄)が永眠いたしましたため 年頭のご挨拶を控えさせていただきました」という一文を添えるようにしましょう。
 |
喪中はがきが届いたらどうする?対応方法や返事の例文をご紹介します 11月の中頃を過ぎると、喪中はがきが届きはじめる時期です。喪中はがきのお返事には3つの方法があります。またそれぞれ注意すべきマナーもあるので事前に理解しておくと安心です。 |
正月飾り
お正月に、玄関に門松や締め飾りを飾ったり、家の中に鏡餅を飾ったりする慣習がありますが、そのような正月飾りは、祝い事としての性質が強いため、喪中期間中は控えるようにしましょう。
年越しそば
喪中期間中でも、年越しそばを食べることは特に問題ないとされています。
年越しそばは「細く長く生きられますように」「健康で長生きできますように」などの願いを込めて大晦日に食べるお蕎麦で、日本の伝統的な食文化の一つですが、お祝いの意味が込められているわけではないため、喪中期間中でも避ける必要はありません。
おせち料理
一方、おせちは新年を祝う料理でお祝い事の一種であるため、喪中期間中は控えるのがマナーとされています。おせちには海老や鯛、紅白かまぼこなど慶事に用いられるおめでたい料理や、祝い肴として知られる黒豆・数の子・田作りなどが含まれていたりするため避けた方がよいでしょう。
ただし、煮物や栗きんとん、酢の物などを日常食の延長としていただく分には問題ないでしょう。かまぼこも白だけにするなどして工夫をすれば、お正月だからといって避ける必要はありません。
お雑煮
お雑煮も、年越しそば同様に長寿や家内安全を願う料理です。伝統的にみればハレの日の料理とも捉えることができますが、中身の餅や野菜は日常食であることから、紅白かまぼこや鯛のようなお祝いを連想させる食材を用いないのであれば、喪中期間であってもいただくご家庭が多いです。
新年のご挨拶
お正月に誰かとお会いすると必ず「おめでとうございます」と挨拶を交わすことになります。しかし、喪中期間中は「おめでとうございます」ではなく「今年もよろしくお願いします」などと挨拶した上で、喪中であることを丁寧に伝えるようにしましょう。
初詣
忌中期間(四十九日の忌明けを迎えるまでの期間)は神社への参拝を避けるべきですが、それ以降の喪中期間であれば、神社へ参拝すること自体は問題ないとされています。ただし、お正月の初詣として大々的にお参りをするというよりは、松の内(1月7日までの期間)を避けて、自分やご家族の健康や安全を祈る気持ちで参拝するのがよいでしょう。
お年玉
お年玉は渡し方を工夫すれば、渡しても差し支えないでしょう。
今でこそ現金をあげることが一般化しているお年玉ですが、もとを辿れば、年神様の魂の拠り所となる鏡餅を、家長が家族に分け与えていたことが由来となっています。そうすることで年神様からの生命力を体内に取り込み、その年を健康に過ごせると考えられていたのです。
そのためお年玉は、「年神様からの贈り物」であり、新しい年の始まりを祝う慶事の意味合いが強い慣習ということができるため、なるべく控えた方がよいとされています。
ただし、お年玉として渡すのではなく「お小遣い」や「書籍代」「おもちゃ代」などと称して、ポチ袋も祝い事を連想させない控えめなものを用いるなど工夫をして渡せば問題はないでしょう。また、お年玉を渡す場合の挨拶も「おめでとう」ではなく「今年もよろしくね」などといって渡すようにしましょう。
大切なことは故人を偲ぶ気持ち
これまでお伝えしてきたように、「祝い事を避け、身を慎む期間」とされている喪中期間中は、お正月であっても、おせちや年賀状、正月飾りなどの祝い事は避けるのがマナーとされています。しかし現代においては、生活スタイルや価値観の変化から、昔ほど厳格ではなくなってきています。
そのため、今回お伝えしたことも、最終的には個人や家庭の判断に委ねられている部分が大きいといえるでしょう。あまりマナーにとらわれすぎず「故人を偲ぶ気持ち」を大切にして過ごしていれば、それがそのままよい供養につながるのではないでしょうか。
栃木・茨城・静岡・愛知・群馬・宮城のご葬儀は、家族葬のタクセルで
家族葬のタクセルでは、栃木・静岡・愛知・群馬・宮城での家族葬や一日葬を安心の低価格で承っています。まずはお見積もりだけでも、お気軽にお問い合わせください。
もし、葬儀や納骨のことなどで疑問やご不安があれば、家族葬のタクセルの事前相談をご活用ください。専門の相談員が、24時間365日無料でご相談を承っています。どんなに些細なことでも構いませんので、お気軽にご相談ください。
家族葬のタクセルの無料相談はこちらから
お見積もり・葬儀のご依頼は下記までお電話ください。
栃木県・茨城県 0120-633-009
静岡県 0120-83-3020
群馬県 0120-880-514
愛知県 0120-574-247
宮城県 0120-486-141
家族葬のタクセル ホームページはこちらから
家族葬のタクセルのお葬式
✔️少人数対応の家族葬専用の式場
✔️お近くの火葬場で直葬・一日葬も対応
✔️費用を抑えた低価格のお葬式を実現
✔️葬儀前から法要まで充実のサポート
✔️24時間365日、いつでもご依頼・ご相談可能
✔️中部エリアでテレビCM放映中

 お急ぎの方へ
お急ぎの方へ 無料相談
無料相談 資料請求・
資料請求・ 供花注文
供花注文