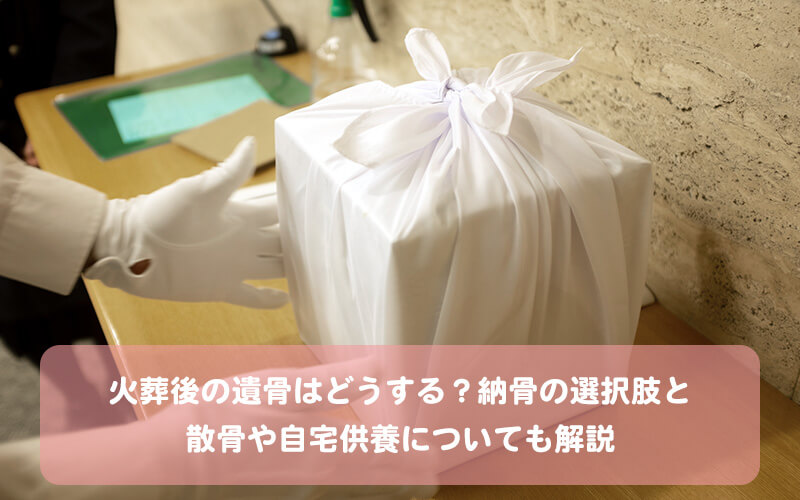
火葬を終えたご遺骨は、お墓へ納骨されることが一般的です。
しかし、最近は、納骨堂や樹木葬、自宅供養や海洋散骨など、一般的なお墓へ納骨する以外の選択肢も増えています。また、ご遺骨を先祖代々の墓と自宅などに分骨するという方法をとる場合もあるでしょう。
そこで今回は、火葬後のご遺骨の扱い方について、納骨・散骨・自宅供養・分骨などといったさまざまな選択肢をご提示しながら解説したいと思います。
目次
火葬から納骨までの流れ
葬儀を終えた後、故人様の棺は火葬場へと運ばれ荼毘に付されます。火葬を終えたご遺骨は、火葬に立ち会ったご遺族やご親族によって骨壷に収められ、いったんは自宅へと戻りますが、四十九日の忌明けを迎えたタイミングで、お墓へ納骨されることが一般的です。
また納骨は、四十九日法要や一周忌などの法要とあわせて行われることが多くなっています。
納骨に必要な埋葬許可証について
納骨の際には、埋葬許可証が必要になります。埋葬許可証とは火葬許可証に火葬済の印が押されたもののことをいい、収骨を終えた後、骨壷と一緒に火葬場のスタッフから渡されることが一般的です。
この埋葬許可証がないと納骨ができなくなってしまうため、納骨まで大切に保管しておきましょう。
一般的な納骨の流れ
ここでは、先祖代々のお墓に納骨する場合を想定した納骨の流れを解説します。
【納骨式の準備】
1. 墓地使用許可証を発行してもらう
すでに、お墓を所有している場合は、お墓の管理者から墓地使用許可証を発行してもらいます。
2. 参列者に連絡をする
納骨式は、四十九日法要とあわせて行われることが多いため、法要の準備と一緒にすることが一般的です。
参列いただく方が少ない場合は、電話などで個別にご連絡してもよいですが、人数が多い場合は納骨式の日時・場所・地図・施主の連絡先などを記載した招待状を作成してお送りしましょう。
3. お供え物や会食の準備をする
納骨式には、お墓へのお供え物として生花やお菓子、果物などのお供え物を持参するため事前に手配しておきましょう。また、納骨式の後に親族で会食の席を設ける場合は、お店を探して料理も手配しておきましょう。
4. お墓の名義変更手続きをする
お墓の名義が故人になっている場合は、誰がお墓を引き継ぐのかを決め、お墓の管理者に連絡します。管理者の指示に従って手続きを行いましょう。
5. お布施や塔婆の準備をする
当日持参する僧侶へのお布施や、お墓に建てる塔婆の手配もしておきましょう。塔婆はお寺に依頼すると授けてもらえます。なお、浄土真宗では塔婆は不要です。
【納骨式当日】
1. 施主挨拶
2. 僧侶による読経と参列者による焼香
3. 納骨
4. 再び僧侶による読経と参列者による焼香
5. 会食
納骨式では僧侶による読経と参列者による焼香を納骨の前後にそれぞれ行います。納骨後の読経は、先祖を供養するための「納骨経」と呼ばれるものです。いずれも読経の途中で施主を筆頭に故人と関係の深い順に焼香を行います。
納骨の選択肢
ここまでは、火葬から納骨までの一般的な流れについてお伝えしてきましたが、次は、納骨先の先選択肢についてご紹介したいと思います。
最近は、先祖代々継承していくお墓以外にも、永代供養といってお墓の管理者に管理や供養を任せることができる納骨先も増えています。また、故人の希望によっては、自然に還すという方法を選ぶこともできます。
一般的な石のお墓に納骨する
ここでは、みなさんが「お墓」と聞いて真っ先にイメージする、一般的な石のお墓について解説します。
一般墓または伝統墓ともいわれ、家族や親族が代々受け継いで管理・供養をしていくお墓のことをいいます。
新しく一般墓を建てる場合は、100万〜350万程度の費用が必要といわれており、お墓の管理には年ごとに管理費がかかります。
・家族や親族がお墓を継承し管理できる人
・伝統や形式を大切にしたい人
・宗教を重んじる人
納骨堂に納骨する
納骨等は、屋内に設けられた納骨スペースに骨壷を納めるスタイルのお墓です。
ロッカー式や仏壇式などさまざまなタイプの納骨堂があり、費用は20万円〜180万円程度が目安です。納骨堂のタイプや納骨する人の数によっても費用は変わりますが、墓石を新しく建てるのに比べると抑えることができます。
また、お墓の継承者がいない場合も、納骨堂が遺骨の管理・供養を行ってくれる永代供養が基本となっており、宗旨宗派も問いません。
・なるべく費用を抑えたい人
・お墓の管理や供養を納骨堂に任せたい人
・宗教にこだわらない人
合祀型永代供養墓に納骨する
複数の遺骨をまとめて一つの大きなお墓に埋葬します。骨壷から出し、不特定多数の方のご遺骨と混ざった形で埋葬されるのが特徴です。
その分、費用は5万円〜30万円程度と大幅に抑えられるため、費用面を最優先に考える方に向いています。
ただし、埋葬した時点で他の方のご遺骨と混ざってしまうため、一度埋葬すると遺骨を取り出すことができなくなってしまう点には注意が必要です。
・お墓の継承者に不安がある人
・お墓の管理や供養を寺院や霊園に任せたい人
・宗教にこだわらない人
集合型永代供養墓に納骨する
複数の方の遺骨を、骨壷に入れた状態でまとめて一つの大きなお墓に埋葬します。
費用は20万円〜60万円程度が相場と比較的安く抑えることができ、合祀墓のように他の方のご遺骨と混ざることはないため、後々別の場所に納骨する可能性がある方は、合祀型よりも集合型を選ぶことをおすすめします。
ただし、他の方と一緒のお墓にはなるため、個別のお墓のように自由に法要を行えない場合があるなどのデメリッもあることを念頭に置いておきましょう。
また集合型でも、33回忌など一定の期間を過ぎた後は、合祀されるケースがほとんどです。何年で合祀されるかは契約時に確認しておくとよいでしょう。
・なるべく費用を抑えたい人
・お墓の管理や供養を寺院や霊園に任せたい人
・宗教にこだわらない人
個別型永代供養墓に納骨する
個人または夫婦などで個別に埋葬スペースを設けて一定期間は個別のお墓として利用でき、その後は、寺院や霊園に管理や供養を任せられるお墓のことです。
費用相場は50万円〜150万円程度で、費用を抑えながらもある程度しっかりと弔うこともできる納骨方法です。
・お墓参りをしたい人
・夫婦だけ・自分だけのお墓が欲しいなどの希望がある人
・将来的にお墓の管理や供養を寺院や霊園に任せたい人
・宗教にこだわらない人
樹木葬にする
樹木葬とは、墓石を建てず、樹木や草花を墓標とする埋葬方法です。
最終的にご遺骨は土に還るため「亡くなったら自然に還りたい」という故人の希望を叶えてあげることができ、費用も抑えられるという理由から人気のある埋葬方法です。
樹木葬にも合祀型・集合型・個別型があり、どのタイプを選ぶかによっても費用は変わりますが、合祀型は5万円~20万円、集合型は20万円~60万円、家族ごとの個別型なら50万円~150万円程度が目安となります。
また樹木葬も、お墓の継承者がいない場合でも、寺院や霊園が遺骨の管理・供養を行ってくれる永代供養が基本となっており、宗旨宗派も問いません。
・お墓の継承者に不安がある人
・なるべく費用を抑えたい人
・お墓の管理や供養を寺院や霊園に任せたい人
・宗教にこだわらない人
納骨以外の選択肢
次に、納骨以外の選択肢についてお伝えします。
散骨をする
散骨とは、火葬後のご遺骨をパウダー状にして、海や山などの自然環境に撒く葬送方法です。
代表的なものに、船に乗って遺骨を海に撒く海洋散骨がありますが、他にも山林に撒く山林散骨や、ヘリコプターなどで空中に撒く空中散骨、ロケットで宇宙に打ち上げる宇宙散骨など様々な方法があり、いずれも自然に還りたいという故人の希望を叶えてあげたいというご遺族に選ばれています。
ちなみに、散骨の費用は散骨方法によっても変わります。海洋散骨の場合で10万円〜30万円程度が相場となっていますが、宇宙散骨の場合は100万円以上になることもあります。
なお散骨は、一度行ってしまうと遺骨が手元に残らないため、お墓や納骨堂のように遺族が偲ぶ場所がなくなってしまうといった注意点があります。また、実際に散骨を行う際は、条例等に遵守したサービスを提供している信頼できる業者を通じて行うことをおすすめします。
・お墓の継承者に不安がある人
・費用を抑えたい人
・宗教や伝統的な供養にこだわらない人
自宅供養(手元供養)をする
火葬後、故人のご遺骨を自宅で保管し、供養する方法です。お墓を持たない供養方法で、手元供養とも呼ばれています。すべてのご遺骨を自宅供養する全骨安置と、一部をお墓に納骨し、一部を自宅で供養する分骨の2種類があります。
安置方法にも、骨壷のまま安置すること以外に、ミニ骨壷を利用したり、一部をアクセサリーやインテリアに加工したりする方法などバリエーションがあります。
自宅安置は、故人を常に身近に感じられるというメリットがありますが、遺骨にカビなどが生えないように保管には細心の注意が必要なことや、家族以外の人がお参りをしにくいことなどが懸念点になります。また、管理している人が亡くなった後の供養方法についても考えておく必要があるでしょう。
・常に、故人を身近に感じていたい人
・お墓参りに行けない人
・宗教や伝統的な供養にこだわらない人
分骨とは
分骨とは、故人の遺骨を複数箇所に分けて供養することをいいます。
たとえば、先祖代々の墓と新しいお墓の2ヶ所に納骨する場合や、先祖の墓から遠い場所に住む親族が身近な場所で供養したい場合などに、一部を自宅に持ち帰り自宅供養するなど、様々なケースが考えられます。
分骨をする場合は、火葬前に火葬場に申し出て、収骨をする際に遺骨を分けてもらう方法がスムーズですが、後から分骨の必要が出てきた場合には、納骨先の管理者に許可を得て、ご遺骨を取り出す方法もあります。
いずれの場合も、分骨証明書が必要になるため、収骨の際に分骨を希望する場合は火葬場で、納骨後に必要になった場合は火葬が行われた市区町村役場で発行してもらいましょう。
自分に適した埋葬方法を知り選択しよう
火葬後のご遺骨は、先祖代々のお墓に納骨することが一般的ですが、最近はそれ以外にも、多様なニーズに対応した様々な選択肢があり、ご自身やご遺族の意向に沿った方法を選ぶことができます。
たとえば、お墓の継承者にご不安がある方は、永代供養付きのお墓を選んだり、自然に還りたいという希望がある場合は、散骨や樹木葬を選ぶこともでき、それによって従来のお墓を購入するよりも費用を抑えることも可能です。
事前に向き不向きや注意点を踏まえておくことが、後悔のない埋葬方法を選ぶことにつながりますので、わからないことは葬儀社や親族、菩提寺などに相談しながら進めていきましょう。
栃木・茨城・静岡・愛知・群馬・宮城のご葬儀は、家族葬のタクセルで
家族葬のタクセルでは、栃木・静岡・愛知・群馬・宮城での家族葬や一日葬を安心の低価格で承っています。また、葬儀に関する疑問やご不安をご相談いただける無料相談も24時間365日承っていますので、電話やメールはもちろん、対面やオンラインなどご都合に合う方法で、お気軽にご相談ください。
家族葬のタクセルの無料相談はこちらから
お見積もり・葬儀のご依頼は下記までお電話ください。
栃木県・茨城県 0120-633-009
静岡県 0120-83-3020
群馬県 0120-880-514
愛知県 0120-574-247
宮城県 0120-486-141
家族葬のタクセル ホームページはこちらから
家族葬のタクセルのお葬式
✔️少人数対応の家族葬専用の式場
✔️お近くの火葬場で直葬・一日葬も対応
✔️費用を抑えた低価格のお葬式を実現
✔️葬儀前から法要まで充実のサポート
✔️24時間365日、いつでもご依頼・ご相談可能
✔️中部エリアでテレビCM放映中
24時間365日、いつでもお待ちしています。

 お急ぎの方へ
お急ぎの方へ 無料相談
無料相談 資料請求・
資料請求・ 供花注文
供花注文