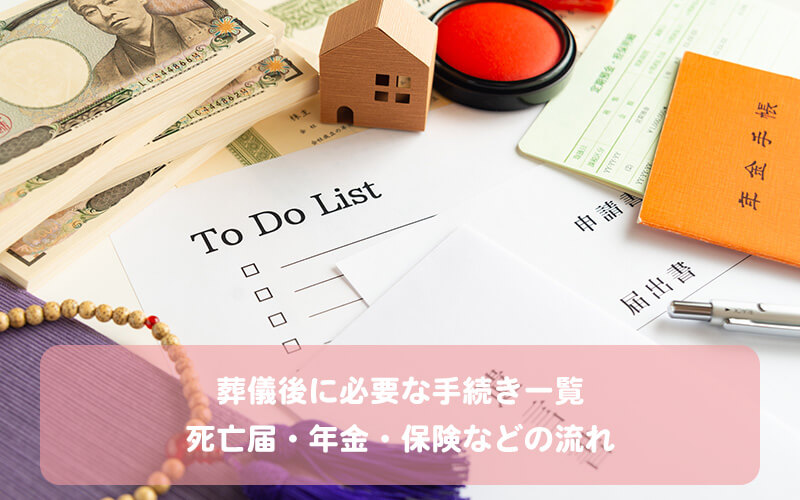
大切な方を亡くされた後にご家族様がするべきことは、死亡届の提出にはじまり、年金や保険の手続き、相続の手続きなど多岐にわたります。お身内を亡くされ、ただでさえご不安な中、事務手続きをこなすことは大変なことですが、期限のある手続きも多いため、優先順位をつけて一つひとつ片付けていくことが大切です
今回は、少しでもお力になれるよう、死亡後や葬儀後にどのような手続きが必要で、どこに申請すればよいのか、必要な持ち物は何か、などをまとめてみました。
死亡後すぐに行う手続き、2週間以内に行う手続き、1ヶ月〜2年以内に行う手続きに分けてご紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
目次
死亡後すぐに行う手続き
死亡後すぐに行う手続きは、死亡届と火葬許可申請書の提出です。死亡届の提出期限は、死亡の事実が確認された日から7日以内となっており、火葬許可申請書と一緒に提出することが一般的です。火葬許可証は火葬をする際に必要になる書類なので、なるべく早めに手続きをしておきましょう。
死亡届も火葬許可申請書も、提出先は故人の住所地の市区町村役場です。死亡後に医師から発行された「死亡診断書」の左側が死亡届になっているので、必要事項を記入の上持参しましょう。ちなみに、死亡届は、後の手続きで添付書類として必要になることも多いので、10枚程度コピーを取っておくとよいでしょう。
また、火葬許可申請書は、市区町村役場の窓口で入手することができます。自治体によってはWebサイトから事前にダウンロードできる場合もあるため確認しておきましょう。
なお、死亡届と火葬許可申請の手続きは、葬儀社が代行してくれることも多いです。担当の葬儀社に確認して頼めるようならお願いした方が安心です。
死亡後、2週間以内に行う手続き
死亡後、2週間以内に行う手続きは以下の通りです。
なお、手続きに必要な持ち物についても記載しておりますが、申請先によって異なる場合があるため、申請前に必ず、該当する提出先が指定する持ち物をご確認の上ご持参ください。
【死亡後、2週間以内に行う手続き】
・埋葬許可証の受け取り
・年金受給停止の手続き
・各種健康保険証の返却
・世帯主変更手続き
・各種サービス等の名義変更・解約
埋葬許可証の受け取り
埋葬許可証とは、故人のご遺骨(骨壷)をお墓へ納骨する際に必要になる書類です。火葬後、故人の焼骨を骨壷に収めた後、骨壷と一緒に火葬場のスタッフから手渡される書類になるため、納骨まで大切に保管しておきましょう。
年金受給停止の手続き・・・死亡後10日または14日以内
故人が年金を受給されていた場合は、年金事務所または年金相談センターで受給停止手続きを行います。この手続きを怠ると年金の不正受給となってしまいますので注意しましょう。
●必要なもの●
・年金証書
・故人の 年金手帳 または 基礎年金番号通知書
・死亡を証明する書類(死亡診断書のコピーなど)
・申請者の 本人確認書類(運転免許証など)
・振込先情報がわかるもの
※年金の振込停止・未支給分返還の手続きに必要
・印鑑
世帯主変更手続き・・・死亡後14日以内
故人が世帯主だった場合、故人の住民票のある市区町村窓口で世帯主変更手続きをする必要があります。
ただし、世帯に残った人が1人だけの場合や誰も残っていない場合、あるいは配偶者と15歳未満の子どものみで新たな世帯主が明確である場合などは、自動で世帯主が決まるため手続きは不要となります。
●必要なもの●
・死亡が確認できる書類(死亡診断書のコピーなど)
・世帯変更届
※自治体によって名称が異なります
・新しい世帯主の確認書類(運転免許証など)
・変更前後の世帯構成を把握できる書類やメモ
・印鑑 など
各種健康保険証の返却
国民健康保険、社会保険、後期高齢者医療保険、介護保険に分けてお伝えします。
【国民健康保険の場合】・・・死亡後14日以内に返却
故人が国民健康保険に加入していた場合、お亡くなりになられてから14日以内に、住民票のある市区町村役場に「国民健康保険資格喪失届」を提出し保険証を返却します。市区町村によっては、死亡届を提出すれば資格喪失手続きは不要となる場合もありますが、保険証の返却は必ず必要になります。
●必要なもの●
・故人の国民健康保険証 (世帯主が亡くなられた場合は扶養者の保険証も返却)
・国民健康保険資格喪失届
・申請者の本人確認書類(運転免許書など)
・死亡を証明する書類(死亡診断書のコピーなど)
・印鑑 など
【社会保険の場合】
故人が会社勤めをしていた場合、加入していた健康保険組合や協会けんぽで手続きを行いますが、会社に手続きを行なってもらえる場合が多いため、まずは会社の総務担当者などに連絡して手続きの流れを確認しましょう。
【後期高齢者医療保険の場合】・・・期限の定めはありませんが死亡後14日以内を目安に返却することが望ましい
故人が75歳以上(一定の障害があるかたは65歳以上)で、後期高齢者医療保険に加入されていた場合は、故人の住民票のあった市区町村役場に返却します。
●必要なもの●
・故人の後期高齢者医療被保険者証(原本)
・後期高齢者医療被保険者資格取得届
・申請者の本人確認書類(運転免許書など)
・死亡を証明する書類(死亡診断書のコピーなど)
・印鑑 など
【介護保険証の場合】・・・死亡後14日以内に返却
故人が65歳以上、または40歳以上65歳未満で要介護・要支援認定を受けていた場合は、故人の住民票のあった市区町村役場に「介護保険資格喪失届」を提出し、介護保険証を返却しましょう。
●必要なもの●
・故人の介護保険被保険者証(原本)
・介護保険被保険者資格喪失届
・死亡が確認できる書類(死亡診断書のコピーなど)
・申請者の本人確認書類
・印鑑 など
各種サービス等の名義変更・解約・・・死亡後すみやかに
水道・ガス・電気などの公共料金の支払いや家賃、携帯代といった各種サービスの名義変更や解約を行いましょう。これらは、放置すると料金が発生し続けてしまうため、早めの手続きをおすすめします。
下記に、名義変更や解約が必要とされるサービスについてまとめてみましたので、参考にしてください。
・水道・ガス・電気・家賃・インターネット利用料・携帯電話・映像や音楽のサブスクリプションサービス・定期購入しているサービス・新聞など
死亡後1ヶ月〜2年以内に行う手続き
ここでは、葬儀後1ヶ月〜2年以内に行う手続きについて、優先順位の高いものから順番にご紹介します。
なお、手続きに必要な書類等について記載しておりますが、申請先によって異なる場合があるため、申請前に必ず、該当する申請先が指定する持ち物をご確認の上ご持参ください。
【死亡後1ヶ月〜2年以内に行う手続き】
・相続準備
・相続放棄や限定承認
・準確定申告
・相続税の申告・納付
・葬祭費/埋葬料の申請
・高額療養費の請求
・国民年金の死亡一時金請求
・遺族年金の請求
相続準備・・・死亡後1ヶ月以内
相続財産を調査し、財産目録を作っておきましょう。また、相続人が誰なのかを確定するために、故人の出生から死亡までの戸籍謄本を取り寄せたり、故人の最終住所地を証明するために住民票除票を取り寄せたりする必要があります。
相続手続きで戸籍謄本や住民票除票の添付を求められることもあるため、なるべく早いうちにこれらの書類を集めておきましょう。また、これらの書類はコピーで代用できる手続きもありますが、原本を求められる可能性もあるため、二度手間を避けるため複数枚取得しておくと安心です。
相続放棄や限定承認・・・相続が開始したことを知った日から3ヶ月以内
故人に借金など負債があって相続を放棄したい場合(相続放棄)や、プラスの財産とマイナスの財産がある場合などに、プラスの財産を限度として借金を返済することを条件に相続をしたい場合(限定承認)は、相続が開始したことを知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てる必要があります。
もし期限を過ぎてしまうと単純承認とみなされ、負債も含めたすべての財産を相続することになってしまうため注意が必要です。
●必要なもの●
・相続放棄申述書/限定承認申述書
・戸籍謄本(全部事項証明書)
※故人が生まれてから死亡するまでの連続した戸籍
・相続放棄をする人の戸籍謄本
・印鑑 など
※住民票の除票または戸籍の附票が必要になる場合もあります。
※限定承認の場合、財産目録・債務目録、財産関係の証拠書類(預金通帳の写し、登記事項証明書、不動産評価証明書、借入契約書など)が追加で必要になります。
準確定申告・・・死亡日の翌日から4か月以内
故人が個人事業主や年収2000万以上の給与所得者、年400万以上の年金受給者だった場合は準確定申告が必要になります。死亡日の翌日から4か月以内に「故人の死亡日時点の納税地の税務署」に提出しましょう。
期限を過ぎてしまうと、加算税や延滞税がかかってしまうので早めに着手しておくと安心です。
●必要なもの●
・申告書類
・源泉徴収票や領収書、控除証明書などの必要書類
・故人のマイナンバーカードや通知カードなどマイナンバーが確認できるもの
・故人の戸籍謄本(全部事項証明書)
・死亡が確認できる書類(死亡診断書のコピーなど)
・相続人全員の印鑑
・相続人代表の本人確認書類
・振り込み口座がわかるもの
・遺産分割協議書の写し など
相続税の申告・納付・・・相続が開始したことを知った日の翌日から10ヶ月以内
相続財産が基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超える場合、相続が開始したことを知った日の翌日から10ヶ月以内に申告・納付が必要です。
申告先は、故人の住所地を所轄する税務署です。期限を過ぎてしまうと加算税や延滞税がかかってしまうので注意しましょう。
●必要なもの●
・戸籍謄本(出生から死亡までの連続したもの)
・住民票の除票または戸籍の附票(死亡時の住所確認用)
・除籍謄本(死亡の記録があるもの)
・故人の所得税の確定申告書控え(過去のものがあれば)
・相続人全員の戸籍謄本
・相続人全員の住民票
・相続人全員の印鑑証明書
・相続関係図(任意)
・財産に関する書類(預貯金残高証明書や通帳コピー、不動産登記事項証明書など)
・債務に関する書類(借入金の契約書、未払の税金や公共料金の領収書、葬儀費用の領収書など)など
葬祭費/埋葬料の申請・・・葬儀を行った日の翌日から2年/亡くなった日の翌日から2年
故人が加入していた健康保険に応じて、葬儀を行った方(喪主)が受け取れる給付金です。申請しないと受け取ることができないため、期限内に忘れずに申請しましょう。
【葬祭費】
故人が国民健康保険や後期高齢者医療制度に加入していた場合に受給できる給付金です。
保険証の資格喪失届けと合わせて申請するとスムーズです。
申請先:故人が加入していた市区町村役場
受給金額:自治体によって異なる(5万円前後)
●必要なもの●
・葬祭費支給申請書
・故人の健康保険証
・葬儀を行ったことを証明する書類(葬儀社の領収書や会葬御礼など)
・申請者(喪主)の本人確認書類(運転免許証など)
・印鑑
・振込先の口座が分かるもの
・葬儀を行なった人の本人確認書類(運転免許証など) など
【埋葬料】
故人が社会保険(健康保険や共済組合)に加入していた場合に受給できる給付金
申請先:故人が加入していた健康保険組合または社会保険事務所
受給金額:一律5万円+付加給付あり
●必要なもの●
・埋葬料支給申請書
・死亡が確認できるもの(死亡診断書のコピーなど)
・埋葬(葬儀)を行ったことを確認できる書類(葬儀社の領収書や会葬御礼など)
・振込先の口座が分かるもの
・申請者の身分証明書
・振込先の口座が分かるもの
・印鑑 など
高額療養費の請求・・・診療を受けた月の翌月の初日から2年以内
医療機関や薬局の窓口で支払った額が、月の初めから終わりまでで一定額を超えた場合、高額療養費の請求をすることができます。負担の上限額については所得や年齢によって異なるためご自身でご確認ください。
申請先は、国民健康保険や後期高齢者医療保険に加入されていた場合は故人の住民票のあった市区町村役場、社会保険に加入されていた場合は、故人が加入していた健康保険組合または社会保険事務所です。
●必要なもの●
・高額療養費支給申請書(加入している 健康保険の様式)
・故人の健康保険証
・医療機関の領収書
・世帯主や本人のマイナンバー確認書類
・振込口座情報
・印鑑
・申請者の本人確認書類 など
国民年金の死亡一時金請求・・・死亡日の翌日から2年以内
故人が国民年金の受給者で、保険料を納めた月数が36月以上あり、老齢基礎年金・障害基礎年金を受けることなく亡くなった場合に、その方と生計を同じくしていた遺族が受け取ることができる給付金です。
市区町村役場申請先は、故人の住民票がある年金事務所や年金相談センターです。
●必要なもの●
・国民年金死亡一時金請求書
・死亡を証明する書類(死亡診断書のコピーなど)
・請求者との続柄を確認できる書類(戸籍謄本(全部事項証明) など)
・申請者の本人確認書類
・振り込み口座のわかるもの
・印鑑 など
遺族年金の請求・・・死亡日の翌日から5年以内
故人が国民年金または厚生年金保険に加入していた場合、故人と生計を共にし、条件を満たした方が受給できる年金です。「遺族基礎年金」「遺族厚生年金」があり、亡くなった方の年金の加入状況などによって、いずれかまたは両方の年金を受け取ることができます。
●必要なもの●
・年金請求書
・故人の年金手帳または基礎年金番号通知書
・請求者の本人確認書類
・請求者と故人の続柄を確認できる書類(戸籍謄本(全部事項証明)など)
・死亡の事実が確認できる書類(死亡診断書など)
・申請者の本人確認書類(運転免許証など)
・振込先情報がわかるもの
・印鑑 など
次の1から4のいずれかの要件を満たしている方が死亡したときに、遺族に遺族基礎年金が支給されます。
- 国民年金の被保険者である間に死亡したとき
- 国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満の方で、日本国内に住所を有していた方が死亡したとき
- 老齢基礎年金の受給権者であった方が死亡したとき
- 老齢基礎年金の受給資格を満たした方が死亡したとき
次の1から5のいずれかの要件を満たしている方が死亡したときに、遺族に遺族厚生年金が支給されます。
- 厚生年金保険の被保険者である間に死亡したとき
- 厚生年金の被保険者期間に初診日がある病気やけがが原因で初診日から5年以内に死亡したとき
- 1級・2級の障害厚生(共済)年金を受けとっている方が死亡したとき
- 老齢厚生年金の受給権者であった方が死亡したとき
- 老齢厚生年金の受給資格を満たした方が死亡したとき
葬儀後の手続きは優先順位を決めて期限内に処理しよう
葬儀後にご家族様が行うべき手続きは多岐にわたります。葬儀や法要の準備で慌ただしい中、これらの手続きを進めることは、体力的にも精神的にも大変なことかと思いますが、期限を過ぎてしまうと受給できない給付金や、延滞料がかかってしまう手続きなどもあるため、優先順位を決めて計画的に進めていくことが大切です。
栃木・茨城・静岡・愛知・群馬・宮城のご葬儀は、家族葬のタクセルで
家族葬のタクセルでは、栃木・静岡・愛知・群馬・宮城での家族葬や一日葬を安心の低価格で承っています。まずはお見積もりだけでも、お気軽にお問い合わせください。
もし、葬儀のことで疑問やご不安があれば、家族葬のタクセルの事前相談をご活用ください。専門の相談員が、24時間365日無料でご相談を承っています。どんなに些細なことでも構いませんので、お気軽にご相談ください。
家族葬のタクセルの無料相談はこちらから
栃木・茨城・静岡・愛知・群馬・宮城のご葬儀は、家族葬のタクセルで
家族葬のタクセルでは、栃木・静岡・愛知・群馬・宮城での家族葬や一日葬を安心の低価格で承っています。まずはお見積もりだけでも、お気軽にお問い合わせください。お見積もり・葬儀のご依頼は下記までお電話ください。
栃木県・茨城県 0120-633-009
静岡県 0120-83-3020
群馬県 0120-880-514
愛知県 0120-574-247
宮城県 0120-486-141
家族葬のタクセルのお葬式
✔️少人数対応の家族葬専用の式場
✔️お近くの火葬場で直葬・一日葬も対応
✔️費用を抑えた低価格のお葬式を実現
✔️葬儀前から法要まで充実のサポート
✔️24時間365日、いつでもご依頼・ご相談可能
✔️中部エリアでテレビCM放映中

 お急ぎの方へ
お急ぎの方へ 無料相談
無料相談 資料請求・
資料請求・ 供花注文
供花注文