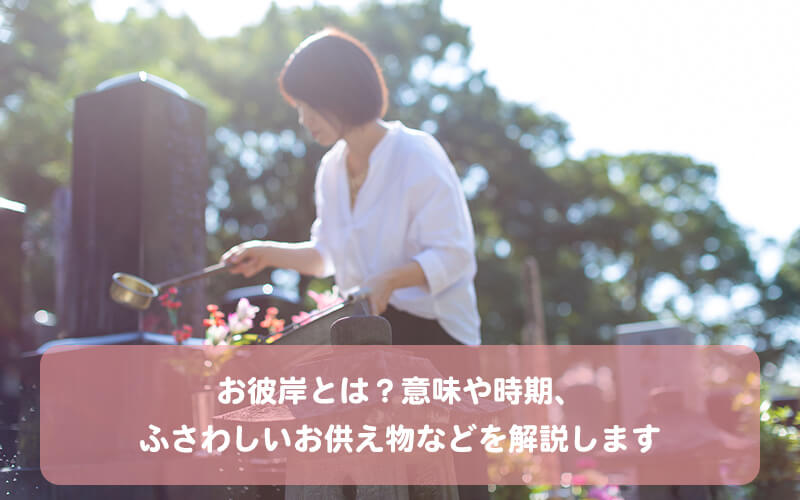
毎年、春と秋に訪れる「お彼岸(おひがん)」ですが、「お墓参りをする日」というイメージはあっても、本来の意味や目的を知っている人は少ないのかもしれません。
そこで今回は、「お彼岸には何をすればいいの?」「お彼岸はいつからいつまで?」などの基本情報を解説しつつ、お彼岸の意味や由来についてもご紹介したいと思います。
お彼岸のお供え物としてよく選ばれている食べ物もご紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
目次
お彼岸とは
お彼岸は、ご先祖様を偲び、感謝の気持ちを表す日本独自の仏教行事で、1年のうち春と秋の2回訪れます。
お彼岸の期間は7日間あり、それぞれ春分の日と秋分の日を中日とした前後3日間がそれに当たります。春分の日も秋分の日も、太陽が真東から昇り真西に沈みむため、仏教では、私たちがいるこの世(此岸)と、ご先祖様たちがいるあの世(彼岸)が最も近づく日と考えられており、古くからその前後にご先祖様を供養する「お彼岸」の行事が営まれてきました。
【春のお彼岸】
春分の日(3月20日または21日のことが多い)の前後3日間
例)3月17日〜23日または3月18日〜24日の7日間
【秋のお彼岸】
秋分の日(9月22日または23日のことが多い)の前後3日間
例)9月19日〜25日または9月20日〜26日の7日間
※春分の日、秋分の日は地球の公転周期によるため毎年変わります。
お彼岸は全部で7日間あり、初日を「彼岸の入り」最終日を「彼岸の明け」といいます。
| 1日目 | 彼岸の入り |
| 2日目 | |
| 3日目 | |
| 4日目(春分の日/秋分の日) | 中日 |
| 5日目 | |
| 6日目 | |
| 7日目 | 彼岸の明け |
お彼岸の起源
お彼岸の起源は、およそ1200年前の平安時代にまで遡ります。この年、桓武天皇の弟であり無実の罪を着せられ亡くなった早良親王の霊を慰めるために、七日間の間、諸国の僧に昼夜を問わず読経することを命じ、初めての彼岸会が行われました。その後、彼岸会は時代を経るうちに、年中行事として広まり一般化したと考えられています。
お彼岸の仏教的な意味
お彼岸は、仏教用語で「悟りの境地に達すること」を意味する「到彼岸」が語源となっており、仏教的には、私たちのいる煩悩に満ちた世界(此岸)から脱し、悟りの世界(彼岸)に達するために行う修行期間とされています。
お彼岸の過ごし方
現代におけるお彼岸は、ご先祖様を供養し、感謝を伝えるための行事であると同時に、家族や親族が集まって絆を深める機会でもあります。
お彼岸といえば、お墓参りをイメージする人も多いと思いますが、ここでは、お彼岸の過ごし方をいくつかご紹介したいと思います。
お墓参りをする
お彼岸の時期は、一年の中でも暑さ寒さが和らぎ、お墓参りをするのにちょうどよい時期とされています。特に、中日となる春分の日・秋分の日にお参りすることがベストといわれていますが、いつ行っても問題はないので、7日間の間でご都合のよいタイミングにお参りをしましょう。
【お墓参りの手順】
1. 掃除をする
・お墓周辺の掃き掃除
・墓石の水洗い
・花立てや香炉などを綺麗にする
2. お供えをする
・水鉢に水をいれ、花立てにお花を活ける
・そのほか、故人の好物などを供える
3. 合掌
・お線香をあげ、合掌し冥福を祈る
※複数人で行った場合は、故人に近い人から順にお参りをします。
4.後片付けをする
・お参りで使ったものを片付ける
・お供物は置きっぱなしにせず持ち帰る
法要に参加する
お彼岸には、寺院や自宅でお彼岸法要を行うこともあります。法要を行うかはお寺やご家族の考え方にもよりますが、お寺で行う場合は合同法要となり、事前にお寺から案内が届くことが多いです。
また、ご自宅に僧侶をお呼びして法要を行う個別法要も可能です。どちらの法要を行うかわからない場合は、寺院に相談してみるとよいでしょう。
いずれの場合も、法要を行う際は僧侶へのお布施が必要になります。また、ご自宅に僧侶をお呼びする場合は、お布施とは別に交通費として「お車代」も必要になることを覚えておきましょう。
【お彼岸法要のお布施の目安】
合同法要の場合:3千円〜1万円程度
個別法要の場合:3万円〜5万円程度 + お車代として 5千円〜1万円程度
※追善供養として、お墓に卒塔婆を立ててもらう場合は、一本あたり3千円〜1万円程度お包みするのが一般的です。
仏壇の掃除をする
お彼岸は、自宅に仏壇がある場合、仏壇の掃除をするのにもよい機会です。仏具を取り出し、細かい埃をはらったり、乾いた布で全体を拭き掃除したりします。その後、仏具を正しく配置し直したら、お供物を供え、お線香をあげてお参りをします。
自分自身を見つめ直す
お彼岸は、仏教においては修行期間でもあります。仏教では「六波羅蜜(ろくはらみつ)」という6つの行いが定められており、それらを実践することで悟りの世界へ到達できると考えられています。
普段から仏教に慣れ親しんでいないという方も、お彼岸をきっかけに、ご先祖様や周りの人、そして自然に生かされていることに感謝をしつつ、自分自身を見直す機会にしてみてはいかがでしょうか。
【六波羅蜜とは】
布施:財産を施す「財施」、教えを説く「法施」、恐怖を取り除く「無畏施」
持戒:戒律を守り、悪い行いをしないこと
忍辱:困難や苦しみ、他からの迫害や非難に耐え忍ぶこと
精進:仏道修行に励み、怠惰にならず努力を続けること
禅定:心を静め、集中させること
智慧:物事の道理を正しく理解し、判断すること
お彼岸のお供えに向かないもの
お彼岸にはお墓や仏壇にお供えをしますが、お彼岸のお供えには向かないものもあるので覚えておきましょう。
お彼岸は、仏教行事ですので、仏教で禁忌とされている肉や魚、卵などの動物性食品や、修行の邪魔になるとされているニンニク・ネギ・ニラ・ラッキョウ・ノビル(またはタマネギ・アサツキ)といった香りの強い野菜を使った食べ物は避けるようにします。また、甘いものでもチョコレートやアイスクリームのような溶けやすいものは日持ちの観点から好ましくありません。
お彼岸のお供えの定番は?
ここでは、お彼岸の定番のお供え物と、その意味について解説します。
おはぎ・ぼたもち
もち米で作ったお餅を餡子で包んだおはぎやぼたもちは、お彼岸のお供えの定番です。厳密には、大きめの丸型で、こし餡で作られたものをぼたもち、小さめの俵形で、つぶ餡で作られたものをおはぎといい、ぼたもちは春に咲く牡丹の花、おはぎは秋に咲く萩の花が名前の由来となっているため、春のお彼岸にはぼたもち、秋のお彼岸にはおはぎをお供えするのが正式です。しかし、最近はスーパーなどで通年を通しておはぎとして販売されていることも多いので、あまり気にする必要はないかもしれません。
おはぎやぼたもちのように小豆を使ったお菓子は、小豆の赤が邪気を払ってくれるとして、お供物としてよく用いられます。また、昔は高級品だった砂糖を使った食べ物をお供えすることで、ご先祖様への感謝の気持ちを伝えるためともいわれています。おはぎやぼたもちをお供えするタイミングはお彼岸の中日(春分の日・秋分の日当日)が一般的です。
お墓にお供えする場合は、お参りが終わったら片付けて持ち帰り、仏壇の場合は、半日〜1日程度お供えしたら、お下がりとしてご家族でおいしくいただきましょう。
お彼岸団子
お彼岸の際に、仏壇やお墓にお供えする食べ物としてもう一つの定番がお彼岸団子です。お彼岸団子は、遠路はるばるこの世にいらしたご先祖様に対するおもてなしでもあり、あの世への手土産の意味合いもあるため、地域差はありますが、お彼岸の初日と最終日にお供えすることが一般的です。
フルーツ
旬のフルーツもお彼岸のお供物として定番です。フルーツを選ぶときは、常温で保存ができ、日持ちするものを選びましょう。りんごやバナナは定番ですが、いちごやかんきつ類、ビワ、梨など、季節を感じられるフルーツもおすすめです。
フルーツをお供えする際は、「高杯(たかつき)」や「盛器(もりき)」といった仏具を利用し、仏具とフルーツの間に半紙を敷いてお供えするとよいでしょう。
焼き菓子や和菓子
クッキーやマドレーヌ、ようかんやまんじゅうなどの焼き菓子や和菓子は、日持ちがよいため、お彼岸のお供物としておすすめです。特に餡子を使った和菓子は、邪気払いの効果もあり、手土産にしても喜ばれます。
また、甘いものが多くなりがちなお供え物の中で、おせんべいのようなしょっぱい系の和菓子はマンネリ化防止に効果的です。ただし、小さいお子さんやご高齢の方がいる場合は、硬すぎないおせんべいを選びましょう。
故人の好きだったもの
上記に関わらず、故人が好きだった食べ物や飲み物をお供えするのもよいでしょう。ただし仏教で禁じられている動物性食品などは、なるべく避けた方がよいとされています。もし好物だった寿司や鰻をお供えしてあげたいという場合は、食べ物の形を模ったロウソクなども販売されていますので、そのようなものを利用してもよいでしょう。
お彼岸はご先祖様を偲び、感謝を伝える大切な行事です
お彼岸は、年に2回訪れる大切な仏教行事です。普段は仏教になじみのない方でも、お墓参りをしたり、仏壇にお供え物を用意したりと、ご先祖様に日頃の感謝の気持ちを伝えるのによい機会でもあります。ぜひ、日本古来から連綿と受け継がれてきた伝統行事に想いを馳せながら、ご家族やご親族とともにご先祖様を偲び、絆を深めるひとときをお過ごしください。
栃木・茨城・静岡・愛知・群馬・宮城のご葬儀は、家族葬のタクセルで
家族葬のタクセルでは、栃木・静岡・愛知・群馬・宮城での家族葬や一日葬を安心の低価格で承っています。また、葬儀に関する疑問やご不安をご相談いただける無料相談も24時間365日承っていますので、電話やメールはもちろん、対面やオンラインなどご都合に合う方法で、お気軽にご相談ください。
家族葬のタクセルの無料相談はこちらから
お見積もり・葬儀のご依頼は下記までお電話ください。
栃木県・茨城県 0120-633-009
静岡県 0120-83-3020
群馬県 0120-880-514
愛知県 0120-574-247
宮城県 0120-486-141
家族葬のタクセル ホームページはこちらから
家族葬のタクセルのお葬式
✔️少人数対応の家族葬専用の式場
✔️お近くの火葬場で直葬・一日葬も対応
✔️費用を抑えた低価格のお葬式を実現
✔️葬儀前から法要まで充実のサポート
✔️24時間365日、いつでもご依頼・ご相談可能
✔️中部エリアでテレビCM放映中
24時間365日、いつでもお待ちしています。

 お急ぎの方へ
お急ぎの方へ 無料相談
無料相談 資料請求・
資料請求・ 供花注文
供花注文